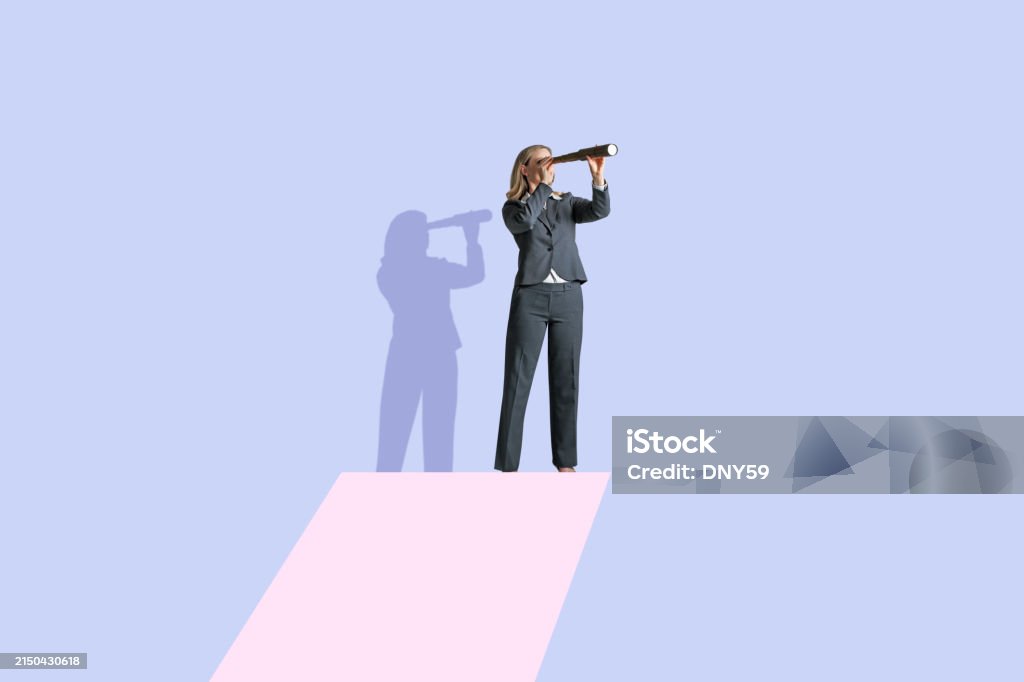言われたことだけだけやってても意味ないよと言われたことはないだろうか。一つの事象から多くを読み取り、相手の予想を上回るアイデアや行動を起こしたいと思う人は多いと思う。こんな時に使える思考法を紹介したいと思う。「メタ思考」である。メタ思とは解決したい問題に対して抽象的にアプローチするものだ。例えば、今彼女が欲しいという思いを抱えているとする。彼女が欲しいという状況をもう少し抽象化すると何でも話せるような仲の良い人が欲しい。といういったように抽象的な問題まで引き上げることができる。彼女という存在に固執せず、友人や家族との時間にも意識を向けられるようになるはずだ。メタ思考で問題を抽象化することで見える景色が変わってくる。こういった問題を抽象的に俯瞰するために有用な考え方や思考法を紹介していくれている良書に出会った。
「メタ思考トレーニング 細谷功 著」である。著書はメタ思考のために2つのポイントを紹介してくれている。「Why型思考」、「アナロジー」である。2つのポイントについて印象的だった所を紹介していこうと思う。
Why型思考
問題解決を試みるときはWhy型思考が有用であると著書の中で紹介されている。疑問詞の中でWhyだけが抽象的な答えを導きだしてくれる。具体的にWhy(なぜ)を使っていこうと思う。
自分は読書が好きだ。なぜ?知らない事を知れるから。なぜ知らない事を知れるのが良いのか?成長できるから。なぜ成長したい?家族や大事な人にメリットを与えられるから。このように読書が好きだという次元の話から、自分の価値観、大事にしているものを深堀することが出来る。自分の思考の土俵を変えてくれる。メタ思考を試みるならWhy型思考と取り入れていくことが重要だ。
他にも、自分がミスを犯した原因を探るのにも、Why型思考は有用である。根本原因を探りたいときにはぜひ利用していきたい。
Why型思考を使う上でのデメリットもある。なぜ?という問いは繰り返し使うことで、問題を深堀できることがメリットだが、これを相手との会話で使いすぎると議論が進まないし、相手にも負荷を与えるため、煙たがられる。自分でじっくり考えたり、今はお互い深い思考をする時間だと共通認識がある場合に利用するべきだ。
アナロジー
アナロジーとは類推を意味する言葉で、一つの事象から示唆される違う視点を見つけることに利用される思考法だ。例えば、道端で人が倒れているときに周りに人が多いほど、自ら助けに出ようする人が少なくなる。逆に周りに自分しかいない場合はほとんどの人が自らその人の元へ駆け寄って助けようとすることが確認されている。人は責任が分散されているほど、行動を起こさなくなる。これを会社に当てはめると人数を増やすほど組織の生産性が上がるわけではなく、一定数で生産性が頭打ちになる事象に関連づけることが出来る。人が多いほど自分の仕事や発現に主体性がなくなっていく。
最初の道に人が倒れているときの対応の事例を抽象化して、人は人数が多いほど責任が分散され行動に移しにくくなるというもの事象を発見した。これを具体化して、会社での生産性の話に繋げた。アナロジーとは抽象と具体の行き来であると著書の中で紹介されている。
こういった具体と抽象の行き来を鍛えるには。物事の関係性の法則を意識してみたり、3つ以上の構成要素に共通点があるかなど、常日頃からアナロジーを鍛えておく必要がある。
具体的な方法としては、上手くいっているビジネスモデルに対して、上手くいっている要因や条件を深堀し、様々な業界に当てはめる妄想をしてみる。著書の中では回転ずしが上手くいった要因を洗い出し、すしを他の食べ物に置き換えたり、食べ物だけでなく、人やモノに置き換えることはできないかといった提案から思考を鍛える設問を用意してくれている。他にも具体と抽象を行き来するための具体的なトレーニングや着目点を紹介してくれている。是非一度読んでみてほしい。
ビジネスモデルを考える際のヒントも著書な中で紹介されている。コピー機とエレベータの共通点は?ビジネス的な答えとしては、どちたもそのもの単体の利益ではなく、購入してもらった後のメンテナンスや補充商品といった、長期的な時間をかけて顧客にサービスを提供し、利益を得るという共通点がある。日常生活でよく使われるものであったり、サービスの利点を意識して共通点を探してみるのもかなり楽しいと思う。
例えば、最近の会話で東京ディズニーランドの話題がでた。圧倒的な接客やアトラクション、世界観でビジネスとして大きな成功を得ている。ここから自分なりにアナロジーを考えてみたい。ディズニーランドでは、一日では把握しきれないほどの、小ネタや作り込みがされてある。何度も行くことで新しい発見や思い出が増えるというのが特徴だと思う。これを他の領域で考えてみると料理の世界でも同じで、同じ料理を何度も作り込んでいく間に、新しい発見があり、よりはまっていくと思う。人は同じ作業の中でも新しい発見があるとはまっていくという性質がある。と抽象化することが出来る。
これをビジネスに応用するとしたら、何度も長期的に商品を買ってもらえるのようにするにはどうすればいいか?何かしらの定期便では中身を毎回ランダムにして、サービス品の組み合わせなども多様性をもたせれば、長期的に消費者が契約していくれるかもしれない。このように自分で何かを予想して妄想するのは頭の体操にもなって楽しい。
まとめ
世の中の情報をただインプットするのではなく、メタ思考を利用して抽象的にとらえなおし、また違う領域に具体的に当てはめてみるといった思考法を紹介してきた。一つの情報から得れるものを何倍にも増やすことが出来るし、何より能動的な情報処理ができると思う。この思考法は常日頃から試していきたい、人生にも色どりが出ると思う。