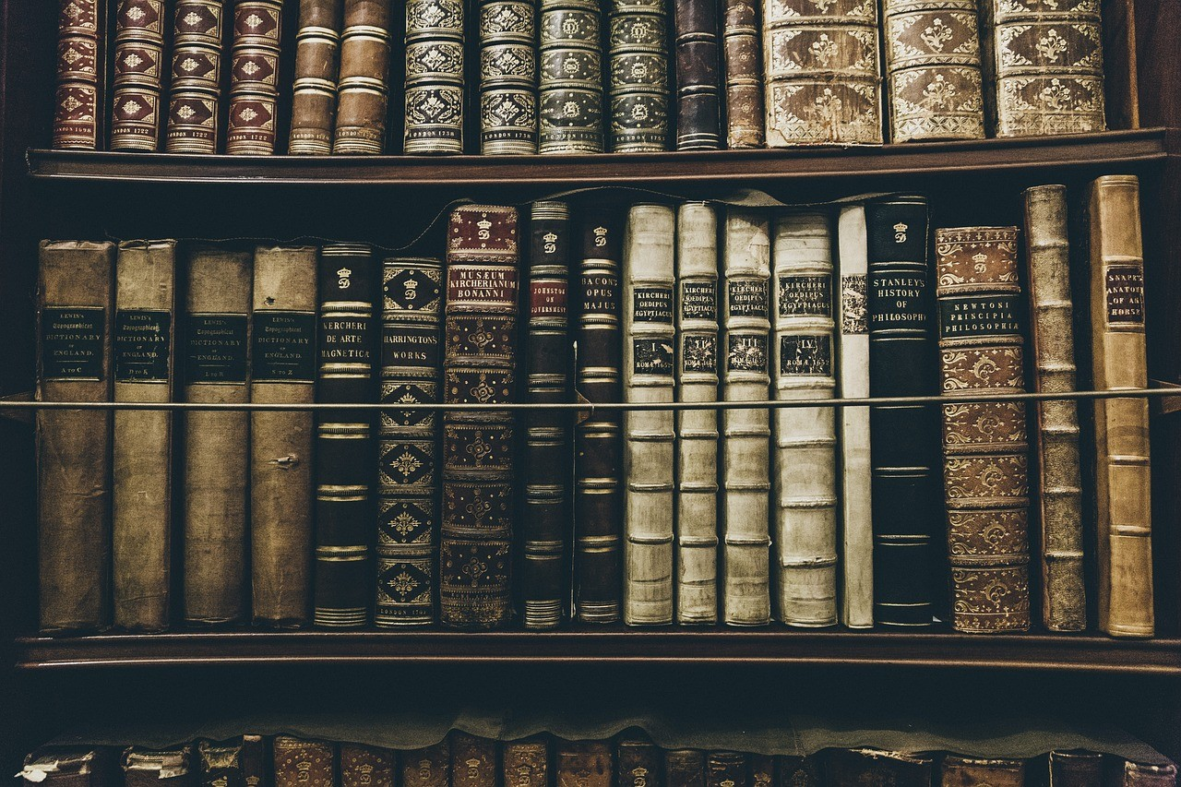ニーチェの考えから自分の生活に活かせることがないか気になっていたところ、良書にであった。「ニーチェ入門 竹田青嗣」である。ニーチェのキリスト教批判やニヒリズム、永遠回帰、力への意思といった考えから、自分たちの生活に活かせるように嚙み砕いて解説できたらと思う。
今回はニーチェのキリスト教批判から学べることを解説してく。
ニーチェのキリスト教批判
物事の良い悪いはかつて、道徳的な観念からではなく、高貴な力をもつ者の行いは良いとされ、もたざるものの行いは悪いというような解釈からきていた。初期キリスト教は力による支配を受ける立場であり、この考えに対抗することができなかった。そこで、彼らは「強者は悪であり、弱者こそ善である」という新しい道徳を生み出し、弱さを美徳として正当化した。弱者が強者を否定するためのルサンチマン的な道徳を生み出したとして、ニーチェはキリスト教を批判した。
また、キリスト教はニヒリズムを生み出した原因であるとも述べられている。
キリスト教は「この世の生は虚しく、本当の価値は死後の世界にある」という考えのもと、利他的に生きていけば天国にいけるという生きる意味を定義している。この考えは今の自分の成長を阻害して、ニヒリズムを生み出すものだといニーチェは指摘している。つまり、今この生きている時間を無価値にしてしまう。
ニーチェの説いたルサンチマンやニヒリズムの考え自分の人生に活かすには?
まず、ルサンチマンは私達の日常にもありふれている。ルサンチマン、つまり嫉妬心は成長のカギにもなりうるが、価値の転倒を引き起こす。金持ちな人やブランド品を身に着けてる人を思い浮かべてくださいといわれた時、あまり誠実そうでない、ちょっと意地汚いキャラクターを思い浮かべる人は多いのではないだろか。自分にないものをもっている人の価値を無意識のうちに下げて手に入れる価値のないものだと自己完結してしまう経験は誰にでもあると思う。
自分の経験としては、スポーツカーに乗っている人なんかには、普通にもっと燃費のいい車あるだろというルサンチマンを抱いていると思う。実際、燃費のいい車の方がいいという一個人の考えは変わらないが、確かにスポーツカーはかっこいいし、ロマンがある。自分の手が届かない価格帯だからといって、価値を否定する理由にはならない。
他にも、自分はあまり愛想がよいタイプではない。そんなに仲良くない人に対してもニコニコしながら対応できない。しかし、職場にはニコニコして誰とでも仲良くしている人もいる。誰でもそんな態度で疲れないのかよ、必要な情報のやり取りできてたら別に必要以上に笑顔ふりまかなくてよくないかと思う自分がいる。自分がそういった態度を取れないからその人の長所を必要のないものだと自己完結している節がある。その人のようにはいかなくても軽い雑談をしたり、笑顔での会話はメリットがたくさんある。ルサンチマンは自分の成長を邪魔してしまうことがあるということが良く分かった。
次は、ニヒリズムについて。ニーチェはキリスト教が死後の世界に価値を見出したことによって、私達が生きている生の世界のでの人生を無価値に変えてしまったという批判をしている。
今現在、日本は無宗教の人が多く死後の世界に価値を見出して生活している人は少ないため、このニーチェの指摘がしっくりこない人は多いと思う。死後の世界にしか価値はないため、今の世界では徳をつみ利他的に生きるべきという考えを一種の固定概念だとすると、自分たちの時代にもたくさんの固定概念が存在しているはずだ。個人でもっている固定概念は違うと思うが、日本人はシャイ、生まれで人生が決まる、学歴がすべて、一度は耳にした言葉だと思う。こういった前提条件に縛られるとできるものもできなくなってしまうし、成長の機会が失われていく。
自分の例を出すと小学生のころから何故か国語の授業が何となく嫌いだった。図書室にいっても図鑑ばかり眺めて小説などを積極的に読まなかった。ただ単に国語の授業をしている先生が嫌いだっただけかもしれないが、その影響は高校生のときまで続いて、古典の授業などは特に苦痛に感じていた。今思えば自分は国語が嫌いだからという理由で国語の面白さを自分から味わいに行かなかった、ただの怠惰だと思う。今は読書が好きで昔の人達の考えにも興味がある。何となく嫌いという固定概念で学びの機会を逃していた学生時代の自分が哀れだ。
まとめ
ニーチェのといたキリスト教批判からルサンチマンやニヒリズムの考えを日常生活に活かす方法を紹介した。二つの概念の影響としてはどちらも自分の成長を止めてしまう可能性があるということだ。簡単にいうと物事を自分のしてんからきめつけてしまう危険性がある。自己成長のためにもぜひ気を付けたい。